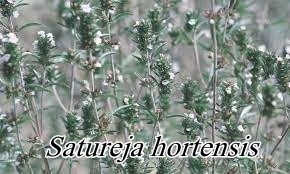目次
はじめの挨拶
皆さんこんにちは。
今回は植物なのに光合成をしないで生きるという生物としてかなり矛盾しているオニノヤガラというハーブについて解説をします。
私も初めて聞いたときはどういうこと?それ植物としてどうなんだい?と混乱しました。

この記事を最後まで読まないとどういうことなのかを知ることが出来ませんし、おそらく他のブログでは取り上げすらしないこの情報を知ることは出来ません。
なのでこの記事はある意味希少価値があり、このブログに来る方は知的好奇心の塊のような方なのでその欲求を満たすことが出来ます。

さらにこの記事は大体1200文字程度なので会社の休憩時間や電車の通勤時間などのスキマ時間に読み切れる長さで忙しい人にもぴったりです。
それでは早速このハーブについて解説をしていきます。
オニノヤガラの生態
約20種類ほどがアジア東部からニュージランドにかけて生息し、人類の歴史に登場したのはAD470年代の中国で、中国漢方の書物に登場しました。
高さは60cm~1m、広がりは約30cm、角張った横に長い地下茎は長さ10~15cm、うろこ状の鞘をまとった茶色の茎と花は茶色がかった緑色をしているのが特徴です。

そのまま中国語を訳すと”天国の麻”といい、その薬効が世界中で注目されてから栽培が試みられています。
このハーブはランの仲間で枝や葉など本来緑色であるはずが茶色。つまり植物が持っているはずの葉緑素を持っていないということです。
それじゃ生きていくための栄養は一体どこから吸収しているのか?

結論を言います。菌類が作り出す栄養に依存して生きているのです。
どういうことかというとまず菌類が動物の死体や有機物を分解して栄養にしますがその栄養を横取りして生きているということです。この形態を菌従属栄養植物といいます。
例えるならば働かずに親のすねをかじっている引きこもりやニートを想像していただき、働いている親を菌類、引きこもりやニートを菌従属栄養植物に置き換えると分かりやすいかもしれません。

あくまで例えで暴言でありませんので悪しからず。
このように菌類に依存すれば自身で光合成をしなくとも生きるために栄養を補給することができるのです。植物の進化の不思議ですね。
薬効
利用する部位は主に根っこの部分で鎮静作用のあるハーブで胆汁分泌促進や平滑筋の痙攣を抑える鎮痙作用があります。
なのでけいれん性の疾患である破傷風やかんしゃくに有効です。他にはリューマチ性の関節炎や肝臓機能不全によるめまい、しびれに効果があります。
栽培の方法
結論を言うとこの植物の生えている環境と合わせて栽培するのがベスト。
日陰の濡れた腐植土豊富な土地に熟した種子をもともと群生している場所に植えるか、樫の木の苗床にきのこと一緒に植え付けるのが良いでしょう。
まとめ
・菌類と共生関係にある
・鎮痙作用がある
・栽培は難しい
あとがき
今回はオニノヤガラという一風変わった特性のあるハーブの解説をしました。
植物の世界には合理性を求めた結果菌類に依存するという興味深い進化を遂げた植物も存在するというのをわかって頂ければ幸いです。
Twitterでは日々ハーブについて発信しているのでフォローするとハーブについてより深く理解することが出来ますよ。@kemu_herbe